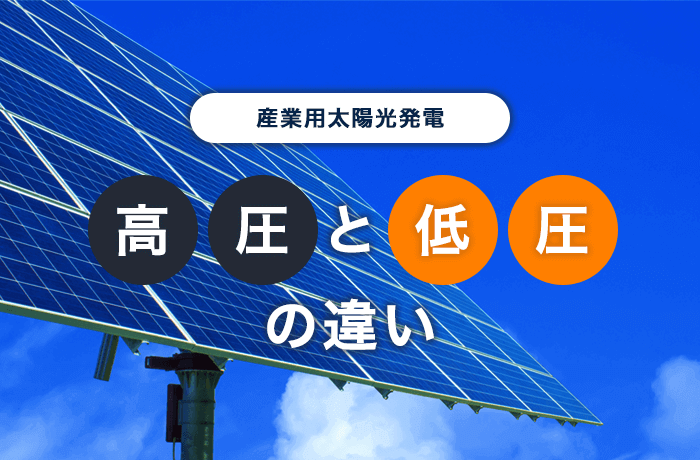
2023年度のFIT発表! 固定価格買取制度の最新情報をこちらの記事で解説しています。
2023年度 太陽光発電FIT価格まとめ[住宅用/低圧/高圧/特別高圧]
太陽光発電の発電容量は、出力によって低圧と高圧に分かれている。法律上の扱いやランニングコストがそれぞれ異なるため、どちらを選ぶべきか悩む人もいるかもしれない。
高圧と低圧の違いを理解せずに設備導入してしまうと、想定以上のランニングコストがかかり、資金計画と実際の運用にずれが生じてしまう恐れがある。
そこで今回は、産業用太陽光発電の高圧と低圧の違い、それぞれのメリット・デメリットを紹介していく。双方の違いをしっかり理解して、間違いのない設備選びをしよう。
太陽光発電の高圧と低圧の違い
太陽光発電は、電気事業法により高圧と低圧に分かれている。高圧とは50kW以上の大規模発電所(高圧連系の自家用電気工作物)、低圧とは50kW未満の小規模発電所(一般用電気工作物)のことだ。
高圧は、法律でさまざまなルールが決められている。経済産業省が提示する技術基準を満たした上で、設備を安全に維持し、管理しなければならない。
保安規定を管轄消防署に提出する、電力会社に毎月基本料金を払う、キュービクル(変圧器)を設置するなど、低圧よりやるべきことが多い。設置や運用の際も、電気主任技術者の選任が必要だ。
一方、低圧の設置は第二種免許の電気工事士でも構わない。電気主任技術者の選任や消防署への届け出も不要だ。規模が小さいため、空き地や倉庫の屋根でも設置できる。
高圧と低圧の設置費用の目安や回収までの日数は?
高圧と低圧は、どちらの方がお得なのだろうか。一般的に、50kW以上の高圧だと初期コストが高くなる。
たとえば、100kWの高圧の方が売電額は多くなるが、50kW未満の低圧の方が初期投資の回収は早い。ここでは、高圧と低圧の設置費用の違いや、初期投資の回収にかかる日数などについて説明しよう。
高圧と低圧の設置費用を比較
100kWの高圧設備と49kWの低圧設備を導入した場合の、費用相場を計算してみよう。2017~2019年の1kW辺りの単価平均相場は、30万円前後である。設備費用は1kWあたり30万円とする。
高圧の導入費用は、3121万円だ。
100kW×30万円=3000万円
キュービクル費用=100万円
電力会社との接続検討費用=21万円
合計金額は3121万円である。
一方、低圧は49kW×30万円=1470万円。
初期費用だけでも、1651万円ほどの差がある。さらに高圧は、電気主任技術者への費用が毎年かかってくる。
年間の売電額と回収までの日数の目安を比較
次に、高圧(100kW)と低圧(49kW)の年間売電額と回収までの日数目安を計算してみよう。簡易的な計算で、システム容量1kWあたりの発電量は1000kWhが目安だ。
売電額は、売電収入×発電量(kWh)で計算できる。高圧(100kW)の売電額の目安は、378万円だ。(100kW×1000kWh×37.8円=378万円)
毎年かかる電気主任技術者への外部委託費用としては、年間6万円ほどかかるのが一般的だ。先程の売電額から差し引いて、高圧の売電収益は372万円になる。(378万円-6万円=372万円)
投資回収までの年数は、約8.4年と計算できる。(導入費用 3121万円÷売電額 372万円≒8.4年)
一方、低圧の売電価格は49kW×1000kWh×37.8=185万2200円、回収までの年数は1470万円÷185万≒7.9年だ。
設置費用と売電額は高圧の方が高いものの、費用の回収は低圧の方が5カ月ほど早くなる。
太陽光発電の高圧と低圧メリット・デメリット
すでに所有している面積が広大な場合、太陽光発電の導入に際し、低圧にするか高圧にするか迷うケースもあるだろう。ここからは、高圧と低圧のメリットとデメリットをそれぞれ説明していこう。
高圧のメリット・デメリット
高圧のメリットは、すでに紹介しているとおり、売電収入が大きくなる点だ。低圧と比べて、1kWあたりのシステム単価が安くなる点も見逃せない。
一方、キュービクル(変圧器)の設置が義務付けられているため、初期費用が高くなるのはデメリットだ。電気主任技術者の選定と選任で、6万円程度のコストもかかってしまう。
低圧のメリット・デメリット
低圧のメリットは、設備にかかる費用が安く小規模なため、参入しやすい点だろう。キュービクル(変圧器)の設置が不要な分、設置費用は安くなる。また、多少土地や屋根が狭くても設置可能な点も見逃せない。
接地面積の計算式は「設置容量×10」である。49kWなら490㎡ほどの面積があれば設置できる。
第二種工事士でも作業ができる、管轄消防署への保安規定の届け出が不要で手間がかからない、電気主任技術者を選任する必要がなくランニングコストがかからない、などの点も魅力だ。
低圧のメリットはたくさんあるが、一つ注意しておきたいことがある。「広い面積があるからランニングコストの高い高圧ではなく、低圧発電設備を複数設置してコストを安く抑えたい」と考える人がいるようだ。
ただし、高圧のメリットである「安い工賃」と、低圧のメリットである「ランニングコストの安さ」の両方を享受できるこの考えは、実現不可能である。詳しい事情を説明していこう。
広い土地で低圧太陽光を複数運用すれば安い?
広い敷地で高圧設備を一つ置くのではなく、複数の低圧設備を作れば管理費用を抑られるのでは? と考える方も居られるだろう。ところが、これは明確に禁止されている。(太陽光発電の分割禁止)
分割案件とは、同一の申請者がひとつの場所に、複数の発電設備を申請することだ。
つまり、同一人物が、同一の地番に複数台の低圧太陽光発電をしても、FIT認定が得られない。事業計画書認定の申請が承認されないケースがあるため、充分な注意が必要である。
それぞれの事業用地の所有者が明らかに違う場合は、分割案件とみなされない。
ただし、従業員や家族、親族などの名義を使うなど、分割案件と思われることを避けるために所有者を分けたと判断されれば、分割案件として扱われてしまう。
分割案件とされた場合、設備所在地と隣接地の登記簿謄本や構図などの提出を求められる。たとえ申請のために急遽所有者などを変更しても、申請日の1年程度前まで遡って調査されるのだ。申請の際は準備や事前の確認などを入念に行おう。
太陽光発電の高圧低圧を理解しニーズにあった方法を選ぼう
産業用太陽光発電は高圧と低圧に区分され、法律上の取り扱いが異なる。事業者に課される義務、運営コストに違いが出てくるのだ。
事業計画をする段階で、投資額や売電による収益、ランニングコストを加味することが重要だ。高圧と低圧の違いを念頭に入れつつ、導入の際にネックになりがちな初期費用を抑えたい。
タイナビNEXTの一括見積もりならコスト削減もしやすいため、ぜひ利用を検討してみよう。



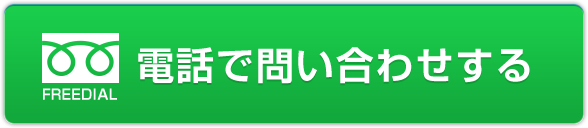

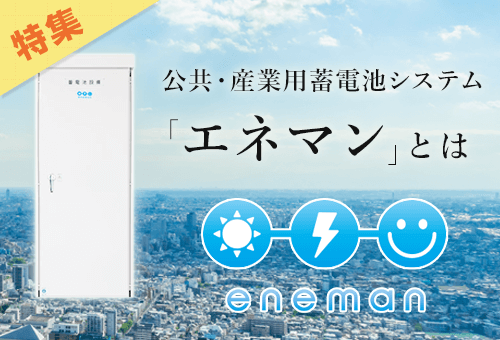
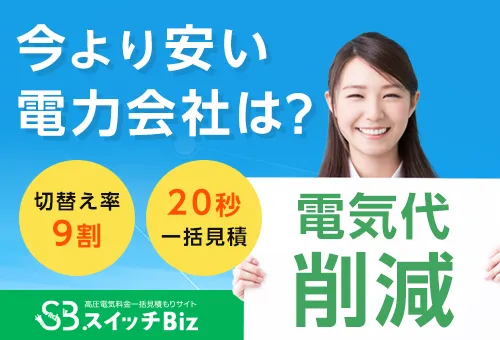


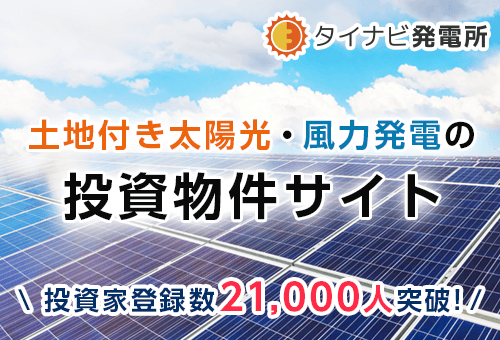
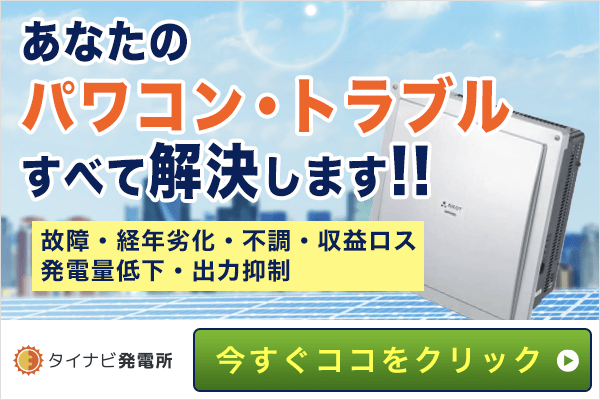

よく読まれている記事
太陽光発電はBCP対策に使えるか? 自家発電システムをもつべき理由
太陽光パネルにはどんな種類がある?素材や形状の特徴
【2025年度】法人向け太陽光発電関連の補助金情報一覧!申請時の注意点なども徹底解説
太陽光発電の土地の広さと規模は?発電量の目安や設置面積の考え方を解説!
使わなくなった農地を有効利用!太陽光発電に転用するためのメリットや注意点
10kW以上太陽光発電「50kWの壁」で変わる手続きと管理コスト